人間は模倣から逃れるのが難しい。
親なり、集団なり、先生なり、多くの人が自然に集団の偉い人を模倣する。
これはおそらく生存のための最適化の本能みたいなものなのか、
どんなに嫌いな親、どんなに嫌いな上役、どんなに嫌いな先生でも模倣するのである。
自分がその集団に所属し続ける限りは、模倣する。
良いことも、悪いことも自然に模倣するのだ。
担任の先生が1年毎に変わるのは非常に良い制度だ。
生徒は模倣せざるを得ないので、その先生の深刻な悪癖を模倣するには1年では足りない。
良いところも悪いところも程よく学んでお別れである。
そうなると怖いのは別れられない場合である。
親や集団は場合によってはすごく長い付き合いになる。そうなると、模倣してしまうのだ。
あの嫌な口癖、動き、態度、はたまた能力まで似てくる。
日本の大企業が官僚機構のようになると、優秀な若い人達を企業の腐敗した官僚文化で汚染して、改善出来なくなる事例がよく発生する。
これはただ腐った部分を模倣して増殖してるのだなと感じる部分が多々ある。かつて所属した誰もが知る大きな会社もそうだったからだ。
日本は長く続けることを美徳とする傾向があるが、それは良い手本がいるときや悪い手本がいないときだけの場合にとどめるべきだと思う。
決して万能な美徳ではない。
先日とても悲しかったのは、尊敬してる先輩の方もやはりその人が嫌悪してやまない上役の行動を無意識に模倣している所を目撃してしまったことだ。
その2人10年以上同じ場所で働いているが、良くないなと強く印象に残ってしまった。
ここまでは嫌な話ばっかりだったが、当然良いこともある。
夫婦なんかは典型かと思う。
最初はあまり自分の趣味じゃなかったものも相手が一生懸命やっているのを長年側で見ていると、同じことをはじめたり、良いものに思えて来たりするのである。
自然と同じ趣味を共有していけたりするのだ。
結婚するときにお互いの趣味が合うかより、はるかに相手に適応する力の方が大切だったりする。
適応力の一部はきっと模倣力なのだろう。
相手の良い部分を模倣する力は人生を良い方向へ導く原動力になるはずだ。

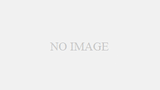
コメント